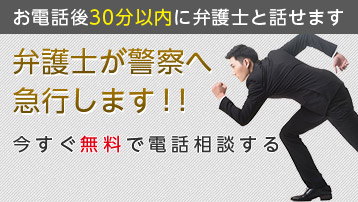不起訴はいつわかる? 不起訴が決まるまでの期間と家族ができること
- その他
- 不起訴
- いつわかる

ご家族など身近な方が逮捕されると、「刑事裁判で裁かれるのか」「前科がついてしまうのではないか」と不安になるのは当然でしょう。
しかし、刑事事件で被疑者となった場合でも、すべてのケースで起訴されて前科がつくわけではありません。令和5年の統計によれば、検察庁で受理された刑事事件(交通事犯を除く)のうち「不起訴」となった割合は、滋賀県内では5割強、全国的には約6割を占めました。
不起訴処分になれば、刑事手続きは終了します。しかし、不起訴処分が決まるまでの間は、被疑者は不安な日々を過ごすことになるため、ご家族のためにもできることをサポートしていきましょう。
本コラムでは、刑事事件における不起訴処分の決定時期や、ご家族ができる具体的な支援について、ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスの弁護士が解説します。


1、そもそも不起訴とは? 不起訴になるとどうなる?
まず、不起訴処分となるとどのような効果を受けるのか、ご紹介します。また、どのようなケースで不起訴となる可能性があるのか、起訴ではなく不起訴になることのメリットや注意点について解説します。
-
(1)不起訴処分の効果
不起訴とは、検察官が捜査の結果を踏まえて、被疑者を刑事裁判にかけない(起訴しない)と判断する処分です。
刑事裁判を提起することができるのはごく一部の例外を除き検察官に限られているため、検察官が不起訴処分をすると裁判は行われず、そこで刑事手続きは一時的に終了します。不起訴処分になれば、もとの生活に戻ることが可能です。
ただし、不起訴となった場合でも、検察官は事件について時効が成立するまでは「再起」(再度捜査を行うこと)して起訴することも可能です。
再起により起訴されるケースはそれほど多くありませんが、被害者への報復行為や同種の犯罪を繰り返すなど、不起訴の相当性を損なうような行動があった場合は、再起されることもあります。
このように不起訴になった場合でも、その後の行動には注意が必要といえます。 -
(2)不起訴処分の種類
不起訴とされるケースについて、法務省が定めた検察事務に関する「事件事務規程」では、20の類型が規定されています。
このうち不起訴になる事例が多い類型について解説します。① 起訴猶予
被疑者が犯人であることが明白な場合でも、被疑者の性格や年齢、境遇、犯罪の内容、犯罪後の情況により、刑事裁判を必要としないと判断されると不起訴になります。
「犯罪後の情況」とは、被疑者の反省の度合いや、被害者への謝罪や示談の成立、周囲に適切な監督者がいるなどの事情を指します。
不起訴処分となるケースの多くは、この起訴猶予によるものです。
② 嫌疑なし・嫌疑不十分
「嫌疑なし」は被疑者が犯人でないことが明白な場合、「嫌疑不十分」は犯罪の嫌疑はあるものの、証拠が不十分な場合に該当します。
刑事裁判にて、有罪判決を得ることが見込めないと判断された際になされる処分です。
③ 親告罪における告訴の取り消しなど
被害者の告訴がなければ起訴することができない罪(親告罪)において、被害者が告訴をしなかったり、告訴を取り消したりしたケースも不起訴となります。
親告罪に該当するのは、過失傷害、名誉毀損、侮辱、器物損壊などの罪です。
これらの罪を犯した場合に、示談が成立し、被害者が被疑者の処罰を望まなくなって告訴を取り消すようなケースが、これに該当します。 -
(3)不起訴のメリットや注意点
不起訴になることの最大のメリットは、前科がつかないことといえるでしょう。
日本の刑事裁判では、起訴されると99%以上の確率で有罪になるのが実情であり、起訴されることで前科がつく可能性が非常に高いといえます。
では、前科がつくとどのようなデメリットがあるのか、また不起訴になった場合でも知っておくべき注意点を解説します。
① 職業等に関する資格の制限
起訴されて罰金刑または拘禁刑に処せられると、職業上の資格について欠格事由となります。このため、新たな資格が得られなかったり、すでに持っている資格が取り消されたりすることがあります。前科による資格制限の対象となる職業や資格
医師、看護師、薬剤師、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、学校教員、公務員、取締役、宅地建物取引士、建設業(一人親方を含む)、警備員など
不起訴になった場合は、資格の制限を受けることはありません。しかし、会社の就業規則に違反して解雇などの懲戒処分を受けることや、取引先の信用を失って事業に影響が出ることは考えられます。
② 履歴書の「賞罰」欄の記載
就職や転職の際、履歴書などに「賞罰」の記載を求められたり、面接などで前科の有無を尋ねられたりした場合、前科については正直に申告する必要があります。
不起訴になった場合は、報道などで知られてしまっているケースが稀にありますが、自ら進んで申告する必要はありません。
③ 海外渡航への影響
海外旅行で必要となる。パスポートの発給について、旅券法13条1項では、以下のような場合に「発給しないことがある」と規定しています。- 長期2年以上の刑に当たる罪で刑事裁判中の場合
- 拘禁刑の刑期や執行猶予期間が満了していない場合
パスポートの発給制限は、主に海外逃亡を防ぐことが目的とされています。
なお、ビザ申請については、前科だけでなく、不起訴となった「前歴」がある場合も、一般の渡航者と異なる取り扱いとなるケースがあります。
たとえば、ビザが不要とされている国でも、前科や前歴の内容を申告してビザの発給を受ける必要が生じることや、そもそも入国を拒否されるケースもあるので、注意しなければなりません。 - 長期2年以上の刑に当たる罪で刑事裁判中の場合
2、不起訴がわかるのはいつ?
不起訴処分となったことがわかる時期は、逮捕・勾留されているか、在宅のまま捜査を受けているかによって大きく異なります。それぞれの場合について解説しましょう。
-
(1)逮捕・勾留された場合(身柄事件)
逮捕・勾留された事件(身柄事件)では、身柄拘束について法律上の時間制限があるため、不起訴・起訴についてわかる時期も比較的明確です。
逮捕されてしまった場合は、以下の流れで手続きが進められます。- 警察は逮捕から48時間以内に検察官へ事件を送致する
- 送致を受けた検察官は24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断する
- 勾留請求がなされ裁判官がこれを認めた場合は最大10日間勾留される
- 勾留期間は原則として最大10日間延長されることがある
このように、身柄事件の捜査は最大23日間に及ぶことになり、通常はこの期間内に起訴・不起訴のいずれかが決まります。
なお、逮捕されても勾留されずに釈放された場合や、勾留中に処分保留のまま釈放された場合は、後述する在宅事件と同じ流れになります。 -
(2)在宅で捜査を受ける場合(在宅事件)
在宅で捜査を受ける在宅事件は、身柄事件と比べると、起訴・不起訴の判断が出るまでにより時間がかかるケースが多いでしょう。
捜査機関側が、時間制限のある身柄事件を優先して処理する必要があることが理由のひとつです。また、在宅事件の被疑者は、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと扱われることから、処理が後回しにされる傾向にあることも理由になります。
在宅事件の場合は、警察から検察への送致(書類送検)に1か月以上かかることが多く、検察官は送致を受けてから、さらに独自の捜査を行い、起訴・不起訴を判断します。
警察で取り調べを受けてから、数カ月後に検察官から呼び出しを受けるということも珍しくありません。
在宅事件の場合、一般的には送致から半年以内には不起訴かどうかが判明することが多いですが、事件の性質や捜査状況によって1年以上かかることもあります。 -
(3)不起訴になったことは通知してもらえる?
検察官には、不起訴処分をしても被疑者に通知する法律上の義務はありません。
身柄事件で不起訴になった場合は、釈放されるタイミングで、留置場の担当官などから「不起訴になった」などと告げられることが多いでしょう。
しかし、在宅事件の場合は、捜査は終わったのか、起訴・不起訴は決まったのかわからないまま時間が経過することがあります。検察庁で取り調べを受け、しばらく何の連絡もない場合、検察庁に問い合わせをして確認するほかありません。
なお、不起訴がすでに決まっている場合は、検察庁に「不起訴処分告知書」の交付を請求することが可能です。この書類はビザの申請で必要になることもあるので、海外渡航の予定がある場合は取得しておくとよいでしょう。
お問い合わせください。
3、不起訴を獲得するために家族ができること
刑事事件でご家族が逮捕・勾留されてしまった場合、不起訴を目指すためには、周囲の方の協力が欠かせません。不起訴を目指すために、ご家族ができる具体的な行動について解説します。
-
(1)弁護士への早期相談
もっとも重要なのは、速やかに刑事事件に精通した弁護士へ相談することです。
ご家族が逮捕された場合、勾留が決まるまでの最大72時間は弁護士以外との面会ができず、被疑者に一切連絡が取れない状態となります。
逮捕直後の取り調べは、起訴・不起訴の判断にも影響する可能性があるため、早期の弁護活動が極めて重要になります。ご家族などから依頼を受けた弁護士であれば、本人と面会して意向を確認したうえで、弁護活動を行うことも可能です。
そのため、ご家族が逮捕されてしまった場合は、できるだけ早く弁護士へ相談しましょう。 -
(2)示談金の準備
不起訴を目指すためには、被害弁償や示談が重要な要素となります。
ただし、被疑者やご家族が被害者へ不用意に接触すると、かえって心情を害されたり、証拠隠滅を疑われたりするリスクがあります。そのため、示談は弁護士を介して行うのが賢明です。
弁護士に依頼する際、ご家族の方は、被疑者に代わって弁償や示談のための資金の準備を行い、必要に応じて示談の場へ弁護士と同席をするといった対応が必要になる場合があります。 -
(3)釈放後の環境整備
再犯防止に向けた環境整備も、不起訴を目指すためには重要な要素です。
ご家族が監督者となり、被疑者が再び同様の問題を起こさないよう、適切な監督ができる環境があることを検察官に示すことで、不起訴の判断につながりやすくなります。
具体的には、以下のような対応が効果的です。- 安定した就労先の確保
- 生活環境や交友関係の見直し
- 必要に応じて、カウンセリングや更生プログラムへの参加や医療機関での治療の支援
4、刑事事件を弁護士に依頼すべき理由
前章では、ご家族の支援について解説しましたが、いずれも早い段階から弁護士と連携して行うことが重要です。
ご家族が本人と面会する場合は、立ち会いの警察官に会話の内容をチェックされて、事件の内容に関する会話は制限されてしまいます。
しかし、弁護士は警察の立ち会いなしで時間の制限なく面会ができるため、取り調べに向けたアドバイスを行うことが可能です。
不当に重い刑事責任を避けるためには、逮捕直後から一貫した供述をすることが重要です。そのためには、弁護士のアドバイスが不可欠といえるでしょう。
また、示談交渉をご家族が行うことはリスクがあるため、弁護士に依頼して適切な示談金額などを検討してから交渉を行うことをおすすめします。
釈放後の環境整備についても、事件の内容や本人の生活環境などによって、最適な方法をアドバイスすることが可能です。
さらに、逮捕・勾留されている場合は、身柄拘束を最小限に抑えるための法的対応も重要です。身柄拘束の必要性が低いことを裁判所や検察官に対して効果的に示すには、弁護士の法律知識や、刑事弁護の実務経験が必要となります。
これらの弁護活動は、身柄拘束が長期化する前に、迅速に着手することでより効果を受けることができるでしょう。
5、まとめ
不起訴が決まるまでの期間は、逮捕されて身柄拘束が続いた場合は原則として最大で23日間、在宅事件の場合は数カ月から半年以上かかることもあります。
起訴されると有罪となって前科がつく可能性が高く、資格制限や就職・転職活動において不利になることも考えられます。
起訴・不起訴の処分が決まるまでの間は不安を抱えておられるでしょうが、ご家族の協力や早期の弁護活動により、有利な処分となる可能性を高めることができます。
ご家族など、身近な方が刑事事件で逮捕された場合には、ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスまでご相談ください。
刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、最善を尽くして弁護活動を行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています