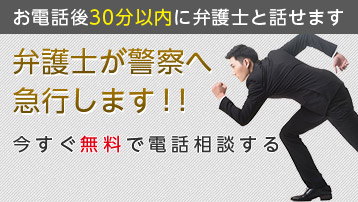微罪処分とはどういうもの? 内容や対象となる犯罪について解説
- その他
- 微罪処分とは

滋賀県警察本部より公表された犯罪統計によれば、令和2年に滋賀県内で発生した犯罪の総数(認知件数)は6039件です。認知された犯罪は、殺人、強盗、窃盗、詐欺、占有離脱物横領などとなっています。このように一口に犯罪と言っても、死刑や無期懲役刑が宣告されるような重大犯罪から、罰金刑が宣告される罪の重さとしては比較的軽微な犯罪までさまざまです。
比較的軽微な犯罪に対しては「微罪処分」という処分が適用されることもあります。「微罪処分」という処分が適用されるには、どのような条件があるのでしょうか。
本コラムでは微罪処分について、具体的な内容やどのような犯罪がその対象となるのかを、ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスの弁護士が解説します。


1、微罪処分とその法的根拠
-
(1)数多い犯罪への対応
令和2年版の犯罪白書によれば、日本国内における令和元年の刑法犯認知件数は74万8559件であり、このうち検挙された件数は29万4206件です。
刑法犯の認知件数自体は平成14年をピークに以後17年連続で減少しているとはいえ、犯罪の数は膨大です。
検察官の数は有限であるため、全ての犯罪を検察官に送致して、検察官に起訴・不起訴の判断をさせることはできないのが現実です。
そこで、犯罪の中でも比較的軽微な犯罪のうち一定の基準に合致する事件は、検察官へ送ることなく警察だけの取り調べで完結させるという手続きを取る場合があります。
このように、警察限りで事件を処理して、事件を終結する手続きを微罪処分といいます。
微罪処分は、全ての事件を検察官に送致した場合に発生する検察官の過大な負担を軽減するために設けられた制度です。 -
(2)微罪処分の法的根拠について
微罪処分は、本来予定されている検察官への事件送致という刑事手続きを行わずに事件を終結させる処分であるため、法律上の根拠が必要となります。
刑事訴訟法第246条は、原則として、警察官が犯罪の捜査をした場合、警察官は検察官へ事件を送致することを定めています。もっとも、例外として、「検察官が指定した事件についてはこの限りではない」と規定しています。この「検察官が指定した事件」という部分の定めが、微罪処分の法的根拠だと理解されています。
また、犯罪捜査規範の第198条から第200条にかけても微罪処分に関する定めがあります。
2、微罪処分の判断主体と対象となる事件
-
(1)微罪処分の判断をするのは誰か
微罪処分にするかどうかを判断するのは、警察です。
微罪処分の適用基準は、検察庁から各都道府県の警察に通達されています。微罪処分の適用の判断にあたっては、警察の裁量もあるため、類似事件の場合でも微罪処分になる場合とならない場合があります。 -
(2)どのような事件に微罪処分が適用されるか
微罪処分の適否を決めるのは警察であり、適用の基準が公開されているわけではありません。もっとも、微罪処分の適否には、おおむね以下の点が考慮されているといわれています。
まず、検察庁が指定している特定の罪名である必要があります。
また、告訴・告発されている場合、基本的に微罪処分が適用されません。
重要な点としては、犯罪被害や犯情が軽微であることがあげられます。
例えば、大けがをさせた、大金を奪ったというような場合は、微罪処分が適用されません。窃盗の被害額であれば2万円以下という額が、軽微と判断される一応の目安となっています。
犯罪をするまでの事情も考慮要素となります。
例えば、つい出来心でやった、思わずカッとなってやったというように、計画性のない突発的な犯行の場合、比較的軽微と評価される傾向にあります。逆に、計画性や常習性があるような場合は、微罪処分は適用されないでしょう。
さらに、被害の回復や被害者の処罰感情も重要です。盗んだ物や壊した物を弁償していた場合、治療費を払っていた場合、被害者が処罰を求めていない場合には、微罪処分を適用して、検察官へ送らないと判断される可能性が高くなります。 -
(3)どのような被疑者であれば微罪処分が適用されるか
微罪処分とするべきか否かの判断にあたり、事件そのものだけではなく、被害者側の事情も考慮されます。
まず、微罪処分が適用されるためには原則として初犯でなければなりません。以前に逮捕されていたり有罪となったりしている場合、つまり前歴や前科がある場合には、微罪処分が適用される可能性が低くなります。
身元引受人がいることも重要な事実です。身元引受人とは、被疑者本人を監督する者を言い、通常は家族や上司がなります。身元引受人のあてがなければ警察も釈放することができず、微罪処分とならない可能性があります。
3、微罪処分を目指すために
逮捕された場合において、警察から検察官へ事件が送致されると身柄拘束期間も長くなり、起訴されて有罪判決を受ける可能性も出てきます。微罪処分が適用されれば、その後に身体拘束を受けることがありません。
微罪処分が適用されるかどうかは警察の判断に委ねられますが、以下のような対応により、その可能性を高めることはできます。
-
(1)取り調べの際に反省の意を示す
まず、警察の取り調べには素直に応じることです。もちろん、本当にやっていないことは否認すべきです。もっとも、本当はやっているにもかかわらず、軽微な罪だからといって否認して反抗的な態度を取れば、悪質性が高いと判断されかねず、また、再犯の可能性も疑われてしまいます。警察が釈放しても問題ないと判断しなければ、検察官に送致されてしまいます。
自分の犯した罪を認め、きちんと供述することにより微罪処分の可能性を高めることができます。
逮捕段階でご家族が被疑者本人に会うことは難しいため、上記の点は弁護士から伝えてもらうとよいでしょう。 -
(2)被害の回復を行う
特定の被害者が存在する場合、被害の弁償をすることが重要です。微罪処分適用の判断にあたって、被害者が被疑者に対し処罰を望むかどうかという点が考慮されます。被害の回復を行った上で示談を成立させることは、微罪処分の適否において重要な要素になります。
逮捕された場合は、本人が直接被害者のもとへ足を運ぶことはできないため、弁護士が示談交渉をすることになります。軽微な犯罪であっても、被害者が強い怒りや不快感を抱くことはありえます。このような場合、本人の代わりにご家族が示談交渉にのぞもうと思っても、うまくいかなくなる可能性があります。まずは、弁護士に相談するのが、示談を成立させ微罪処分が適用されるための第1歩です。
お問い合わせください。
4、まとめ
今回は微罪処分の内容と対象事件を中心にご説明しました。微罪処分は検察送致前の時点での釈放であり、微罪処分が適用されれば、送致された場合と比較して、被疑者の負担を軽減することができます。また、軽微な犯罪だからこそしっかりと反省し、これ以上罪を重ねないように注意しなければなりません。
ご家族などに微罪処分が適用される可能性がある場合、ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスの弁護士までご相談ください。示談交渉や法的なアドバイスを行い、刑事事件の早期解決を目指します。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています