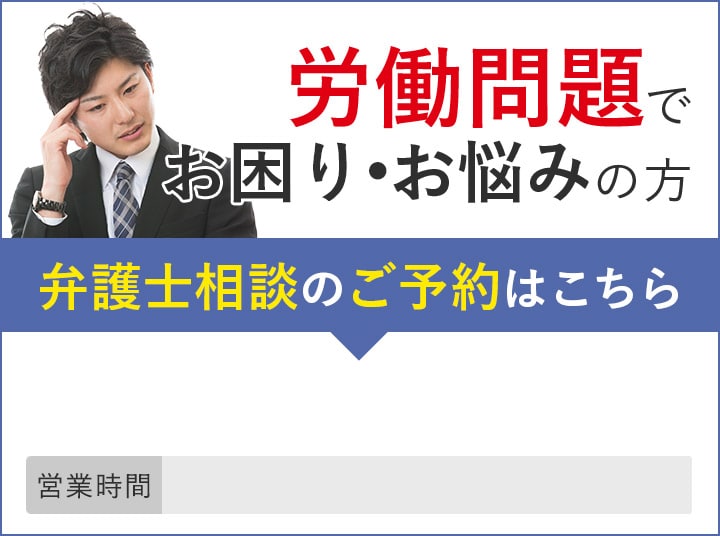週60時間労働は違法なの? 残業代を請求したい場合の対処法
- 残業代請求
- 週60時間労働違法

週60時間労働は違法なのでしょうか。労働基準法(労基法)では、原則として週40時間までが労働時間の上限とされているため、週60時間という労働時間は、決して一般的とはいえません。
そのため、週60時間という労働時間が常態化しているような会社の場合、違法である可能性が高く、また残業代を適切に支払っていない可能性もあります。
この記事では、週60時間労働の違法性、週60時間労働が違法にならないケース、残業代の一般的な計算方法などについて、ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスの弁護士が解説します。


1、週60時間労働は違法?
労働時間については、労働基準法によってルールが定められています。まずは具体的な時間や付与されるべき休日について確認していきましょう。
-
(1)労働基準法における労働時間のルール
労働基準法で定められた労働時間(法定労働時間)は、原則として以下のとおりです(労働基準法第32条)。
法定労働時間- 「1日8時間」以内
- 「1週40時間」以内
休日についても「毎週少なくとも1回」の休日(法定休日)が与えられる必要があります(労基法第35条)。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や、法定休日に出勤させる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)を締結する必要があります。
36協定とは、会社と労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者)との間で取り交わした書面による協定です。36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決める必要があります。
ほとんどの会社では、従業員に時間外労働を命じるために、36協定を締結しています。仮に36協定が存在していない場合、従業員に時間外労働をさせることは法律に違反することになります。 -
(2)時間外労働の上限ルール
会社と労働組合が36協定を締結したからといって、無限に従業員を働かせられるわけではありません。
法律上、時間外労働の上限は原則として「月45時間」、「年360時間」となり(労基法第36条4項)、臨時的な特別な事情がない限りこれを超えることができません。
また、36協定を締結していても、週60時間の労働が繰り返されているという場合には、原則月45時間という残業規制を超えることになるため違法となる可能性が高いでしょう。
なお、臨時的な特別の事情があって会社と労働組合が合意する場合(特別条項)には、残業規制は以下のようになります。- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計が「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」がすべて1月あたり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
2、週60時間労働が違法にならないケース
以下の勤務形態では、週60時間の労働をしても残業とならない可能性があります。
それぞれの勤務形態の概要と労働時間について解説していきます。
-
(1)変形労働時間制
「変更労働時間制」とは、期間内における所定労働時間を平均して、週の法定労働時間を超えていなければ、その期間内の日または週において法定労働時間を超えていても、時間外労働としての扱いをしないという制度です。
労基法には、1か月単位、1年単位、1週間単位、フレックス制の4種類の変形労働時間制が定められています(フレックス制については(3)で後述)。
たとえば、月末に業務が集中し週60時間の労働となったとしても、月の初めが閑散期というケースもあるでしょう。この場合、労働時間を合算して1週間あたりの平均労働時間が40時間以内に収まっていれば時間外労働とはならず、残業代も支払われないことになります。 -
(2)裁量労働制
裁量労働制とは、実際の労働時間ではなく、あらかじめ会社と従業員との間で合意した時間について働いたものとみなして、その分の賃金を支払う制度のことをいいます。
研究・開発、設計などの専門性の高い職種による業務では、始業や終業時刻を含めて労働時間の管理を労働者自身に任せて自由度の高い労働を認めることが効率的な場合があります。
たとえば、みなし労働時間を8時間と合意されていた場合、実際に働いた時間が6時間であっても12時間であっても、8時間分の賃金が支払われることになります。
したがって、裁量労働制が採用されている従業員の場合、実際には週60時間働いていたとしても、残業したことにはならない可能性があるのです。 -
(3)フレックスタイム制
「フレックスタイム制」とは、従業員が始業と就業の時刻を自由に決めることができる業務形態です。
フレックスタイム制で従業員が労働すべき時間として定められた期間を「清算期間」といいます。この清算期間内で、会社が従業員に労働すべきであると定める期間を「総労働時間」といいます。
たとえば、「1か月の清算期間中に総労働時間150時間」といった形で労働時間が決まることになります。
フレックスタイム制を導入した場合には、従業員が日々の労働時間を自ら決定することとなるため、「1日8時間・週40時間」という法定労働時間を超えて労働しても直ちに時間外労働となるわけではありません。
ただし、清算期間において、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が時間外労働としてカウントされることになります。
また、清算期間が1か月を超える場合には、以下が時間外労働としてカウントされることになります。- 1か月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間
- 清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
フレックスタイム制のもとで時間外労働について上記のように考えられているため、週60時間労働したとしても直ちに残業となるとは限らないのです。
3、正しい残業代の計算方法は?
残業代の基本的な計算方法については、以下のような計算式によって算出することになります。
「①基礎賃金」とは、基本給に一定の各種手当を加えた1時間あたりの賃金額のことをいいます。月給制の場合は、1か月当たりの賃金額を1か月の所定労働時間で割ることで賃金額(基礎賃金)を計算します。
1時間あたりの基礎賃金は、以下の計算式によって算出することができます。
なお、1か月の平均所定労働時間については、以下の式で計算することができます。
「②残業時間」とは、基本的には「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えて働いた時間(法定外残業時間)のことを指します。
なお、会社が定めた所定労働時間が6時間とされていて7時間働いた場合は、法定労働時間8時間の範囲ないとなるため、法定内残業時間となります。
上記のような法定内残業をした場合、会社は残業した1時間については賃金を支払う必要がありますが、割増賃金の支払いは必要ありません。
一方、法定外残業をした場合は、所定の「③割増率」によって増額された割増賃金が支払われることになります。
法定外残業、休日労働、深夜労働をした場合の割増率は、以下のとおりです。
- 法定労働時間を超える労働をした場合の割増率:25%
- 月60時間を超える時間外労働をした場合の割増率:50%
- 法定休日に労働をした場合の割増率:35%
- 深夜労働(午後10時~午前5時に勤務)をした場合の割増率:25%
ただし以上のような計算方法は、あくまで基本的な残業代の考え方です。前述したように雇用形態や給与形態によっては、残業代計算の方法が異なってくる可能性がありますので、ご自身のケースで残業代を正確に計算したいという方は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
4、未払い残業代を請求したい際の対処法
-
(1)残業していた証拠を収集する
未払いの残業代を請求しようとする場合、残業代がいくら発生しているのかを証明するための証拠が必要となります。残業代について会社とどのような取り決めになっているのか、どれくらいの時間の残業が発生しているのかといった点を明らかにする必要があるのです。
具体的には、以下のような資料を収集する必要があります。- 雇用契約書、就業規則、労働条件通知書
- タイムカード、出勤簿
- 出勤、退勤に関する業務報告・メール
- 交通系ICカードの改札通過時刻の履歴
-
(2)会社と交渉する・労働審判・訴訟
未払いの残業代が発生している場合、会社に支払うよう交渉する必要があります。
しかし従業員と会社との話し合いではスムーズに解決に至らないことも少なくありません。その場合、労働審判や民事訴訟など裁判手続を利用することができます。
まず労働審判は、裁判所を介して当事者が自らの言い分を主張し話し合いによって解決したり、審判によって判断したりする手続きです。
労働審判によっても解決できなかった場合には、民事訴訟に進みます。訴訟手続きでは、双方が証拠に基づく主張・立証を行い、最終的には裁判所の判決によって判断されることになります。 -
(3)弁護士に相談する
未払いの残業代について会社と揉めそうな場合には、早い段階から弁護士に依頼しておくことがおすすめです。
弁護士に依頼しておけば、客観的な証拠収集のアドバイスや適切な残業代の算出をはじめ、会社との交渉や裁判手続きについてもすべて対応を任せることができます。
また、弁護士が代理人についた場合には、会社との交渉や和解内容も納得いく結果になる可能性も高くなり、個人で交渉するよりもスムーズに紛争が解決できるケースもあります。
お問い合わせください。
5、まとめ
週60時間労働が常態化している場合には、労使間で36協定を結んでいる場合であっても、違法となる可能性があります。ただし、解説したとおり勤務形態によっては週60時間労働が違法とならないケースも存在しています。
したがって、ご自身のケースで正確な残業代を計算したい場合や、未払いとなっている残業代を会社に支払ってもらいたいという場合には、労働問題の実績がある弁護士に相談することがおすすめです。
ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスの弁護士は、労働トラブルについての解決実績がありますので、ぜひ一度ご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています