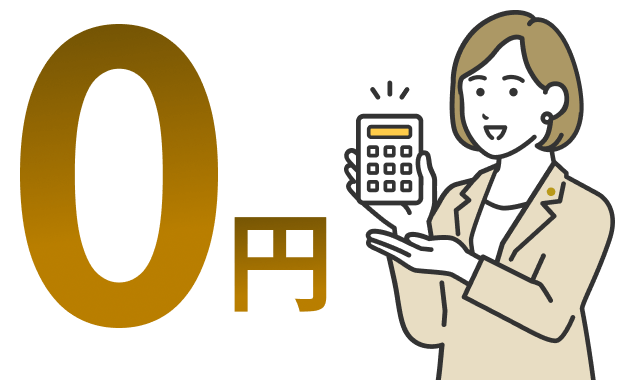遺言能力とは? 遺言者に認知症の疑いがある場合の対処法を解説
- 遺言
- 遺言能力

滋賀県の推計によると、2018年10月1日から2019年9月30日までの1年間における滋賀県内の出生数は1万1083名、死亡数は1万3291名でした。
認知症などを理由として意思能力が低下している場合、遺言書を作成したとしても無効とされてしまう場合があります。
遺言が無効になると相続人間での紛争を誘発してしまうため、認知症の家族などが遺言書を作成する際には、遺言能力があったことを後から証明できるような資料を確保しておきましょう。
この記事では、遺言をする際に必要となる遺言能力について、ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスの弁護士が解説します。
(出典:「滋賀県推計人口(令和元年(2019年)10月1日現在)の概要」(滋賀県))


1、遺言能力とは?
遺言は、遺言者が自らの死後に財産を処分する行為という性質を持ちます。
財産の処分は重要な法律行為ですので、遺言には「遺言能力」が必要とされています(民法961条、963条)。
-
(1)遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識できる意思能力
遺言能力とは、自らの作成した遺言の内容を理解し、財産が相続人にどのように相続されるかを弁識するに足る意思能力をいいます。
遺言を作成することは法律行為であるため、遺言者は意思能力を有していることが必要になります。
そのため、遺言を行う際には遺言能力が必要とされているのです。 -
(2)遺言能力がない状態で作成した遺言は無効
遺言能力がない状態で行われた遺言は無効となります。
典型的には、遺言の内容が自分にとって不利であることがわかった相続人が、遺言を作成した当時において被相続人に意思能力がなかったことを理由として、遺言の無効を主張することにより、紛争が発生するケースがあります。
2、遺言能力の判断基準
遺言当時に遺言能力があったかどうかを判断する際には、以下に挙げる要素が考慮されます。
-
(1)15歳以上であることが必要
遺言を行うには、15歳以上であることが必要となります(民法961条)。
通常の法律行為であれば、未成年者(現在は20歳未満)が行う場合には、原則として法定代理人の同意が必要です(民法5条1項本文)。
しかし、遺言は死亡に際しての最後の意思表示であり、本人が望むのであればその意思を尊重すべきと考えられていることから、通常の法律行為よりも年齢要件が緩和されています。
とはいえ、法律行為の意味や効果を正しく理解できる年齢について一応の基準を設ける必要はあるという考え方の下、民法は15歳以上の者にのみ遺言能力を認めているのです。 -
(2)制限行為能力者でも遺言を行うことはできる
未成年者以外にも、成年被後見人・被保佐人・被補助人は、通常の法律行為をする能力が一部制限されています。
しかし、遺言については本人の意思を尊重すべきという趣旨から、これらの制限行為能力者でも、遺言を行うことはできます(民法962条)。
ただし、成年被後見人が遺言をする場合は、事理弁識能力(自らの行為によって、何らかの法的な責任が生じる状態を認識できる能力)を一時的に回復している必要があるほか、医師2人以上の立ち会いなどが必要です(民法973条1項、2項)。 -
(3)遺言能力の有無を判断するための考慮要素
遺言能力の有無を判断する際には、遺言の内容を理解し、その結果を弁識できるかどうかについて、実質的な観点からも検討がされます。
具体的な考慮要素は以下のとおりです。
- 遺言当時の年齢(高齢になるほど遺言能力が認められにくくなる)
- 心身の状況、健康状態(特に認知症などの進行度)
- 遺言当時やその前後の言動(筋の通った発言などがあれば遺言能力が認められやすい)
- 遺言についての意向を示す別の資料(別の資料からわかる遺言者の意向に沿った遺言内容になっていれば、遺言能力が認められやすい)
- 遺言者と受遺者の関係性(疎遠だったはずの親類に多額の財産が贈与する内容になっている場合などは、遺言能力がないことを疑わせる)
- 遺言自体の内容(遺言の中に事実誤認や矛盾がないかなど)
3、遺言能力に関する紛争事例を裁判例に沿って紹介
遺言能力について実際に争われた裁判例をいくつか見てみましょう。
-
(1)公正証書遺言の無効が主張された事例
公正証書遺言は、公証人が作成する公文書であることから、法的な有効性に疑義が生じにくい形式の遺言として知られています。
しかし、遺言能力の欠如を理由として、公正証書遺言の無効が主張された裁判例はいくつか存在します。
たとえば、和歌山地裁平成6年1月21日判決では、遺言当時75歳を超えていた被相続人の公正証書でした土地建物を長女に相続させる旨の遺言の有効性が争われました。
この事案では、被相続人は、終日介助を要するようになっていましたが、普段の意識は清明であり、公証人の人定質問にも的確に答えていることなどから、遺言当時に遺言能力があったものと認定されました。
一方、大阪地裁昭和61年4月24日判決では、肝硬変と肝がんの合併症などによって昏睡(こんすい)状態に近い状態だった当時81歳の遺言者が作成した公正証書遺言について、遺言能力の有無が争われました。
この事案では、公正証書遺言作成の翌日に遺言者が死亡しており、遺言当時も意識状態が著しく低下していたことに加え、遺言の内容もかなり詳細であったことなどを考慮して、遺言能力が否定されました。 -
(2)死亡危急時遺言の無効が主張された事例
死亡が間際に迫った状態で行う遺言(死亡危急時遺言、民法976条1項)は、証人3人以上の立ち会いが必要とされていますが、複数の相続人などが結託して、自分たちに都合の良い内容の遺言書を作成させてしまうことも考えられます。
東京高裁平成3年11月20日決定では、遺言当時96歳の高齢だった男性による死亡危急時遺言について、遺言能力の有無が争われました。
この事案では、遺言者とそれほど親しくないはずの知人に預金債権を遺贈する内容の遺言になっていたことや、老衰による心臓機能の低下がかなり深刻であったことなどを理由として、遺言能力についての審理をさらに尽くさせるため、事件を原審に差し戻しました。
4、遺言能力がないために遺言が無効とされないための注意点
認知症などの状態にある人が遺言を作成する場合、後に遺言能力が争われることがないように、周囲の親族がサポートしながら適切な対策をとっておきましょう。
-
(1)遺言当時の判断能力を証明する資料を保存する
遺言能力の有無が争われるのは遺言者の死後ですが、遺言能力の基準時は遺言を行った時点となります。
そのため遺言能力の有無は、遺言当時の状況を示す資料などから推認することで判断されます。
たとえば、- 遺言当時に近い時期に遺言者が作成した文章
- 周囲の親族などが作成した遺言者の様子に関する日記
- 遺言当時の遺言者の様子を撮影した動画
- 医師の診断書
などから、遺言者が遺言当時に十分な判断力を有していたとうかがわれる場合は、遺言能力が認められる可能性が高くなるでしょう。
-
(2)公正証書遺言を作成する
上述のように公正証書遺言でも、遺言能力の有無が争われるケースはあります。
しかし、自筆証書遺言の場合に比べると、公証人のチェックが入っている分、遺言能力が否定される可能性は低くなります。
公正証書遺言には、遺言能力以外の観点からも、遺言の有効性をより確実にする効果があり、また家庭裁判所の検認が不要となるメリットもあります。
5、遺言能力を争われた場合の対処法は?
遺言者の死後、遺言能力に関する争いが発生してしまった場合には、遺言者の意思を尊重すべきと主張する側と、遺言の無効を主張する側に、親族が分かれてしまいます。
この場合、法廷闘争が泥沼化し、親族間に決定的な亀裂が入ってしまう可能性も否めません。
ご自身の権利を確保しつつ、親族間の亀裂を最小限に抑えるためには、お早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
ベリーベスト法律事務所では、遺言の有効性を示す資料などがないかについて、弁護士が依頼者とともに検討したうえで、法的な観点から他の相続人に対する説得を試み、遺言能力を巡る争いの穏便な解決を目指します。
また、遺言能力が訴訟で争われることになった場合には、訴訟準備や訴訟中の主張・立証活動において依頼者を最大限サポートいたします。
お問い合わせください。
6、まとめ
遺言能力が否定された場合、遺言全体が無効となり、遺言者の意思が相続に全く反映されなくなってしまいます。
相続人間での遺言能力に関する紛争を防ぐためには、遺言当時の遺言者の意思能力を証明できる資料を残しておくことが大切です。
万が一遺言能力を巡る紛争が発生してしまった場合には、ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスにご相談ください。遺言・相続に関する経験を豊富に有する弁護士が、依頼者の親身になって対応いたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|